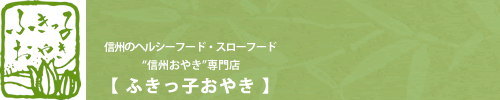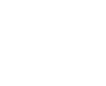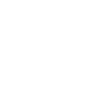おやきってなあに?

■ おやきとは
 “おやき”は一言でいうと“野菜を小麦粉でつつんだおまんじゅう”です。
“おやき”は一言でいうと“野菜を小麦粉でつつんだおまんじゅう”です。
“おやき”は、昔からおばあちゃんやお母さんが家庭で野菜やお漬物を具にして、小麦粉で包み、焼いていました。
時代が変わっても母から娘へ、姑から嫁へと、作り方も味も受け継がれ、連綿と守られてきた信州の代表的な郷土食です。
■ おやきの歴史
そもそもの信州おやきのルーツは、長野県西山地方でつくられる“灰焼きおやき”といわれています。
農作業の合間や夜なべ仕事の傍らで、囲炉裏の灰の中に入れて焼き、食していました。
現在のおやきに進化を遂げていった過程には、囲炉裏から釜戸への移行があります。衛生的かつ短時間で作れる“焼いて蒸かすおやき”に、さらに短時間でできる“蒸かすおやき”に変わっていったようです。
“おやき”はいつごろ誕生したのでしょうか?
 小麦や米、木の実などを粉にし、水を加えて練り上げ平たくし、焚き火や囲炉裏で両面を焼いたものが、おやきの原点です。
小麦や米、木の実などを粉にし、水を加えて練り上げ平たくし、焚き火や囲炉裏で両面を焼いたものが、おやきの原点です。
今から約4,000年前の縄文時代に、すでにおやきはつくられており、長野県西山地方で発掘されています。
それから時が経ち、野菜の具を入れるおやきもつくられるようになりますが、いわゆる“灰焼きもち”が信州おやきの原点といわれています。
中山間地のほとんどの農家でつくられていた“灰焼きもち”は、囲炉裏と共に生まれました。
山間では昼夜を問わず囲炉裏の火を絶やさず、おやきはオキの中で焼かれ、保存食としても重宝されました。
しかし、囲炉裏から釜戸への移行が、現在の“蒸かすおやき”や“焼いて蒸かすおやき”に変化する主因となっていきます。囲炉裏の灰を払って食べるおやきよりも、釜戸に焙烙を乗せて両面を焼き蒸かすおやきの方が柔らかく衛生的という理由もありました。
■ さまざまなおやき
 現在“おやき”と呼ばれているものには、種類が多くあります。
現在“おやき”と呼ばれているものには、種類が多くあります。
“灰焼きおやき”、“焼いて蒸かすおやき”、“蒸かして焼くおやき”、“蒸かすおやき”、“揚げるおやき”など。
また、生地も小麦粉だけでなくそば粉や米粉を入れてつくるおやきもあり、膨らし粉やイースト菌を入れたパン系のおやきもあります。
呼び名もまた“おやき”だったり、“焼きもち”、“焼きまんじゅう”、“まんじゅう”ともいわれています。
このように“おやき”が多種多様になったのは、各地域で生産される穀物の種類が違うことや、それぞれの地域の食文化、慣習の違いであることなど複数の理由が挙げられます。
■ おやきを食べる習慣
 “おやき”は、信州では昔から仏事と深く関わりがあり、春と秋のお彼岸にはご先祖さまにおやきをお供えし、8月1日(石の戸)にはご先祖さまのお墓掃除におやきをつくり、お盆の8月14日にはおやきを仏前にお供え、朝食にする習慣があります。
“おやき”は、信州では昔から仏事と深く関わりがあり、春と秋のお彼岸にはご先祖さまにおやきをお供えし、8月1日(石の戸)にはご先祖さまのお墓掃除におやきをつくり、お盆の8月14日にはおやきを仏前にお供え、朝食にする習慣があります。
また山間地では、この他にお正月や大晦日におやきを食べる習慣が、今でも残っています。
このように、信州では“おやき”が人々の生活と密接に結びつき、現在まで地域ごとに“おやき”が作り継がれてきました。
■ おやきの特徴
“おやき”の特徴は、何といっても、その手軽さにあります。
手ごろな大きさで、手に持ったままかじることができる。
おにぎりやサンドイッチ類の軽食感覚で、おやつにも食事にもなり、持ち歩きも邪魔にならない。
しかも、栄養面では完全食。
おにぎりやサンドイッチと違って、たんぱく質、炭水化物、ビタミン、ミネラルが手軽にバランスよく摂取できます。
■ 【ふきっ子おやき】のおやきは?
【ふきっ子おやき】は、上記にあげたおやきの種類では“焼いて蒸かすおやき”に分類されます。このおやきの流れは、西山地方でつくられている“灰焼きおやき”が里に降りてきた最初の地、更級(さらしな)地方の製法で、焙烙(ほうろく)で焼いた後に、セイロで蒸かすおやきです。
灰焼きおやきがルーツとすれば、灰焼きに一番近い製法でつくられているということ。手間がかかるおやきです。膨らし粉やイースト菌を使っていないため、小型でも小麦粉の量は多く、ボリュームがあります。
 作り方は“水取り”と呼ばれ、生地の水分が多いのが特徴です。
作り方は“水取り”と呼ばれ、生地の水分が多いのが特徴です。
加水率が高い(120%)ため、生地を手に取った瞬間に素早く丸めないと、生地が指のすき間から流れ落ちていってしまいます。熟練の技が必要となる難しいおやきなのです。そのため、この水取り製法で更級地方のおやきをつくっている店舗は、長野市内でも2件しかありません。
また食材や調味料は、自然なものをより多く取り入れるように心掛けているため、たんぱく質、炭水化物、ビタミンはもちろんですが、ミネラル分が非常に多いおやきとなっております。
おやきについて、理解していただけましたか?
理解したら、つぎはぜひ食してみてくださいませ!